トランプ大統領が次々と繰り出すMAGA政策は、先行きがまったく不透明な混乱を世界の政治経済、さらには社会にもたらしている(MAGAは Make America Great Again「アメリカを再び偉大に」の頭文字を並べた略語で、トランプが推進する政策全般の標語である)。
その「アメリカに対する貿易黒字国がアメリカの富を搾取している」「移民が不法に流入してくるので貧困な白人層がますます虐げられている」等々の主張に一理があるのは確かで、思いはわからなくもないが、それにしてもトランプのやり方でよいとは思えない。第二次世界大戦の終結後、80年にわたってアメリカを盟主とし、その掲げてきた自由と民主主義の旗の下に結束してきた同盟国や友好国を翻弄する意図が奈辺にあるのか、もはや不快とはいわずとも不可解である。その動揺を捉えて新興の覇権国家が蠢(うごめ)き出しているのを、政権幹部は知らぬわけもないであろう。
わが国についての最近の状況は、7月7日付の石破首相宛の大統領書簡で「日本の相互関税は25%とし、8月1日から課す」ことが通知(SNSで書簡の写真が公開)された。これは去る4月2日に全世界の国と地域について「基本は10%、それに上乗せする税率を日本は14%」としていたものを、同9日に90日間の停止があって交渉中だった。赤沢大臣がホワイトハウスで赤い帽子を被ったのはその際だが、7月9日に期限が来る前に、さらに3週間の交渉継続が決まったことにもなる。
今回、書簡で通知された14カ国は4月の数字と同じが韓国(25%)、南アフリカ(30%)、インドネシア(32%)、タイ(36%)の4カ国、引き上げが日本とマレーシア(24%→25%)、引き下げが8カ国で、基準も異なる理由もよくわからない(その後もブラジルは50%、ベトナムは20%とか、逐次、発表)。もっともトランプのディール(交渉の駆け引き)のやり方は、就任から半年で、TACO(「トランプはいつもビビる」Trump Always Chickens Out)と皮肉られるように、仕切り直した期限も数字も、またまた動かないとも限らない。
ウクライナのゼレンスキー大統領には「交渉のカードがない」と難詰したトランプに対して、日本はどういうカードを持っているのか。NATO諸国が防衛費をGDPの5%まで増額する決議をしたのは、とりあえずご機嫌を取って嵐が過ぎるのを待つ姿勢を見せたに過ぎない。目標年の2030年には、トランプ自身がホワイトハウスの主でないのは間違いないから、そこでまた交渉すればよいと踏んだからである。かつてアメリカに従った形で平和憲法を制定し、現在は関連経費を含め1.8%近くという日本はどのように振る舞えばよいのか。例えば兵器を買って5%クラブの会員資格を得ようとするのは、経済力からも国民感情からも無理というものだろう。
買うのはコメかガスか
トランプは昨今、アメリカ産米を交渉材料にしたらと誘いかけてもいる。江藤拓前農水大臣が失言で更迭され、それを奇貨として後任の座に就けた小泉進次郎大臣は、JA(農協)を米国資本に売り渡そうとするかもしれない。かつて父親が郵政民営化の大騒動を起こした結果、サービスは低下したうえに赤字化で郵便料金を値上げし、規律も緩んで運送事業の許可を5年間も停止される事態を招いてしまった。令和の米騒動の犯人探しにJAが狙い撃ちされているのは、政敵を「抵抗勢力」と決めつけて刺客を送った手法を想起させるから、これもいつか来た道だろう。JA(特に商社機能の全農)を株式会社化すれば、その株が売買可能になって、いずれ外国資本の手に落ちる恐れもある。食糧安全保障は国民にとって最も守らなければならない砦(とりで)だと、どれだけの人に覚悟があるだろうか。
次に日本に買わせたいのは、天然ガスだろう。折から、トランプがアラスカの天然ガスを交渉材料に持ち出して来たとの話が浮上している。
アラスカは1867年に帝政ロシアから購入した飛地(とびち)で、1959年、ハワイとともに星条旗に星を加えた(49番目、ハワイが50番目)。アメリカで最も広く、最も人口密度が低い州で、最後のフロンティアと呼ばれている。その北部、北極海沿岸のノーススロープ郡プルドーベイにある油田から天然ガスを採掘し、南岸(太平洋岸)のニキスキまでの1300kmを、既設の石油パイプラインに平行してガス・パイプラインを新設して運び、液化したうえで日本、韓国、台湾などの消費国まで海上輸送しようという構想である。6月2日には、トランプ政権のバーガム内務長官、エネルギー情報局のライト長官がダンリービー州知事とともに説明会を開いたが、日本は経済産業省の松尾経産審議官やJOGMEC(エネルギー・金属鉱物資源機構)の担当者を派遣した。
この計画の総事業費は約6兆円という巨額にのぼるが、需給の状況や生産コストが価格に見合うかなど、検討しなくてはならない課題も多いといわれる。プルドーベイの天然ガス埋蔵量は2兆8000億㎥、LNG換算で20億tである。これは日本の年間輸入量の30倍以上になるが、長期にわたる事業への投資だけに経済的リスクのみならず、アメリカの政権交代による政治リスクも十分に考慮しなくてはならない。
アラスカの天然ガスは、1969年に東京ガスと東京電力が初めて輸入してから半世紀の歴史がある。三菱商事がその代行業務を担ったが、今回のアメリカ側からの提案だけでなく、油田のある北極海沿岸で液化して、そこから(南部へのパイプラインを使わず)海上輸送でアジアへもたらす方法も検討されている。温暖化が続いて北極海の凍結期間が短くなった場合のコスト計算、ロシアとの国境であるベーリング海峡を通過することの地政学的リスクなど、考慮すべき課題はたくさんある。
2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が始まってから、LNGについては本欄で何度も取り上げてきた。直後の4月号は状況が流動的なまま「ウクライナ侵攻とエネルギー」というタイトルで、世界シェアが断然1位の25.3%だったロシアからパイプラインで供給を受けていたEU諸国のエネルギー事情は一変すること、日本も出資するサハリン1からエクソンモービルが撤退を表明、日本の全輸入量の7.8%を供給していたサハリン2からもシェルが撤退表明などで想定されるその後の懸念を記している。翌5月号では、「脱ロシアが脱炭素を促すか」と題し、侵攻が長期化し占領の既成事実化が進む中で、そしてロシアに対する経済制裁が発動されるなど、EU諸国も日本も、ロシアの天然ガスが入らなくなる事態にどう対応できるかを問うている。
侵攻から半年、戦況が一進一退を続けていた同年9月号では「天然ガスを武器とする戦争」と題したが、ロシアを国際的な金融決済システムから排除したにもかかわらず、資源大国である強みを発揮してEUの結束を揺るがそうとする「エネルギーバトル」を論じている。バルト海の海底に敷設し、ドイツを経て各国に天然ガスを送るパイプライン「ノルドストリーム1」の流量を制限することでEU諸国を手玉に取る危険が警告されていたのに、ロシアへのエネルギー依存度を高めてしまったドイツの首相たち(1998年からのシュレーダー、2005年~2021年のメルケル)を嗤(わら)うかのように牙をむいたプーチンは、その戦略をエリツィン政権の大統領府副長官だった1997年に著した博士論文で力説していたことを紹介している。
その翌月の「解なきサハリン2の将来展望」(10月号)は、西側諸国全体がソ連邦の解体と非共産化したロシアを過信し、G8の一国に遇するなど致命的誤りを犯したことについて述べている。
LNG輸入の現況
もともとサハリン2は、1994年にシェルが55%、三井物産25%、三菱商事20%の持ち分で設立された西側の合弁会社だったサハリン・エナジーが、サハリン州(旧樺太)北東部の天然ガスを採掘するプロジェクトである。2009年に本格稼働を開始したが、成功が予見されるに至った2006年にロシア政府が強権を発動。プーチンと気脈を通じた
国有ガスプロム社が50%+1株を取得して、従来の株主3社の持ち株を半減させてしまった経緯があった。ウクライナへの侵攻前、日本は全世界から輸入するLNGの7.8%をロシアから受け入れていたが、そのほとんどはサハリン2だった。
侵攻から3年半がたった現在、サハリン・エナジーの資本はシェル撤退分の譲渡先が決まらないままガスプロムが計77.5%を実質支配しており、三井12.5%、三菱10%は変わらず、2025年6月現在、輸入が継続されていることが確認されている。なお、日本のLNG輸入の現状は右の通りである。
| 輸入元 | 万t | % |
| オーストラリア | 2661 | 41.0 |
| マレーシア | 1024 | 15.8 |
| ロシア | 627 | 9.7 |
| アメリカ | 582 | 9.0 |
| カタール | 500 | 7.7 |
| インドネシア | 400 | 6.2 |
| ブルネイ | 300 | 4.6 |
| パプアニュー | 200 | 3.1 |
| その他 | 194 | 3.0 |
(計6488万t)
*はパプアニューギニアの略。輸入した後、韓国、中国、台湾、インド等に、発電所、ガス供給事業への投資とセットで転売されている分も含む。
湯川裕光
作家。1950年、東京に生まれる。東京大学法学部卒業。『安土幻想』『小説古事記成立』など歴史小説を書き、『マンマ・ミーア!』『異国の丘』など、劇団四季のミュージカルの台本も手掛ける。『瑤泉院』は稲森いずみ、北大路欣也主演でテレビ東京の正月10時間ドラマの原作になった。現実政治に携わったこともある。
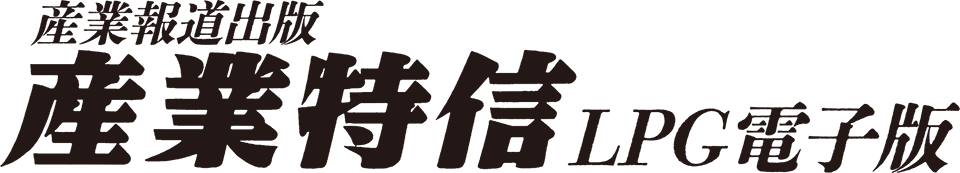

付号_ページ_01-120x68.jpg)
