専門家は難しいこと知っているが、やさしいことも難しく語る癖がある――こう喝破したのは誰であったか。同感する私は、だから本稿では電池について「非専門」の立場で述べることにしよう。
まず「電池」を見て、私たちはそれが電池だと認識する知識を持っている。円筒型で長さは5cm弱、太さは単1から単4まで4種類あって、透明にラップされて店頭で売られている、ということは常識の一つだろう。しかし実際には、円形のボタン電池もあり、年配の方はそれを見ても「これが電池?」と思うかもしれない。それにしても、円筒型でもボタン型でも、池らしきものはどこにもないのに「池」というのはなぜだろうか。専門書を見ても、その答え
は書いてないのが普通である。専門家にはそれも常識だからであろう。
そこで「非専門」を標榜する本稿は書いてしまう。初期の電池は、電解液という液体を角形の槽の中に溜めていたから、それを池に見立てて「電気を起こす池」と呼んだのである、と。しかし後述のように、技術の進歩に伴い電解液を流動状の液体でなく、ジェル状に変えたのだが、以前のものを湿電池とすれば、以後のものを「乾電池」と区別すべきとなった。もちろん乾電池とは形容矛盾だが頓着しなかったために、この変な用語が定着してしまったと考えられる(これは訳語の問題で、英語の battery には池の意味はない。燃料電池は fuel cell だが、起電装置で、乾電池のような蓄電池ではなく、 cell の原義も小さな構造物で、区画、細胞や監房にも使う)。
電池について、本欄では電気自動車(EV、FCV)や資源と関連して「自動車のエネルギー革命」(2023年6月号)や「南鳥島の深海にレアアース」(2024年8月号)で触れたことはあるが、電池の機能を正面から扱ったのではなかった。そこで、本号では一次電池の発明と開発の各段階について、次号では二次電池の究極の形である全固体電池に至るまでを扱ってみたいと思う。
電池の原型については、第一次世界大戦後、オスマントルコ帝国から独立したハーシム家イラク王国(1958年の革命以後は共和国)の首都で1932年に発見された「バクダッド電池」が話題性もあって名高い。が、紀元前の遺物とされる壺が近代の電池の構造に似ているというだけで、これで電気を発生させた痕跡はなく、半ばアラビアンナイトの世界の話である。
やはり良く知られている「ライデン瓶」は電気を溜めることができる装置で、18世紀にオランダのライデンで、ドイツ出身のクライストが原理を考察、ミュッセンブルーク(英語ではマッシェンブレーケ)が実際に製造した。1752年に米国のフランクリンが雷の中に凧を上げて電気をライデン瓶に導いたことで知られ、自然現象である雷が電気の働きだと解明した意義がある。これは電池でなく蓄電器だが、ハンドルを手回しすれば力学的に静電気を発生させることができるから、人体に用いて治療する医療機器にもなった。長崎のオランダ商館から江戸幕府に献上された記録もあり、医師・本草学者で発明家の平賀源内は1776年に破損中の物を手に入れて修理し、見世物にして小銭を稼いだことも知られている。
1780年、イタリアのガルバーニは解剖用のカエルにメスを入れたとき、足が痙攣(けいれん)するのは筋肉に電気を溜める働きがあるからだと主張したが、同じイタリアのボルタは、カエルとは関係ないと実験で否定(メスが後述する2種類の金属片の、カエルの体液が電解液の役割をして電気が発生)した。その後の1800年、ボルタは亜鉛と銅の金属片を正と負の極、希硫酸を電解液とする装置を作って1V(今、誰もが使っている電圧の単位ボルトは、ボルタの名に由来する)程度の電気を化学的に発生させられることを証明したが、この「ボルタ電池」により、カーライル(英)の水の電気分解、デービー(英)のカリウム分離、エルステッド(デンマーク)の磁場の発見、オーム(独)やファラデー(英)の名前を冠した法則など、19世紀前半の電気化学が著しい進歩を遂げるのに貢献した。
基本は正負の極と電解液
話を電池に戻すと、ボルタの電池は発生を始めると終わるまで自己放電が止まらない。理論的には理系の技術本を参照していただきたいが、素焼きの板で隔壁を作り、電解液を2槽に分けることで放電を調整して長持ちさせる。そうして工業的に利用できるようにしたのが「ダニエル電池」(1836年)である。
このダニエル電池はエジソンが1882年に最初の火力発電所を作ってニューヨーク市中に電気を供給するまで、発電機として実験に利用された。日本に持ち込まれたのは1853年にはオランダから、翌年のペリー再航の際には文明の象徴として持参され、電信機の実験にも使われたが、実はそれ以前の1849年に佐久間象山がオランダ語の文献からダニエル電池を製作しており、電気で電信の実験も行われている。
1866年、ルクランシェ(仏)は負極に亜鉛、正極に炭素と二酸化マンガン、電解液に塩化アンモニウム水溶液を用いて、水素の発生を抑制して長期の使用が可能な「ルクランシェ電池」を考案した。これを改良したのがガスナー(独)で、基本的には従来型と同様の「マンガン電池」である。電解液の役割も同じだが、布に沁み込ませてあるので、例えば運搬の際に傾いてしまっても液漏れにならない。したがって「液状の湿電池」に対して、これ以後は「乾電池」という括りになる。この電解液がこぼれ出ない工夫で、ガスナーは1888年にドイツと米国で特許を取得した。実は同じ頃、日本の屋井先蔵(やいさきぞう)も電解液を和紙に沁み込ませるなどの製品を開発したが、特許の知識も資力も乏しく、日本での特許を出願したのが1892年になっていた。
日本電池工業会などによると、屋井の発明は1887年でガスナーよりも1年早かったが、屋井の出願が1892年10
月4日(特許は翌年11月21日)、海軍省の技師だった高橋市三郎の出願は同年の10月15日(特許は翌年10月13日)である。これらは特許内容が違う技術(例えばガスナーは電解液を石膏で固め、屋井は和紙の他、正極の炭素棒にパラフィンを沁み込ませた)なのでいずれも認められて却下されていない。つまり、特許権の争いではなく最初の発明者は誰なのかという話である。
と同時に、実際の製品の優劣もある。1894年に日清戦争が勃発すると日本陸軍の備品だったルクランシェ電池は厳冬の満洲では電解液が凍結して使い物にならず、急遽、陸軍省から発注があり、屋井乾電池が大量に納品されて電灯や通信機の電源として実戦に役立つことが証明されたのである(高橋は海軍の佐世保海軍工廠で電気部の主任技師だったが、日露戦争後、岡田嘉助創業の日本乾電池製造で研究を続けた)。
乾電池であるマンガン電池は市場に広く普及したが、1980年代に性能が上回る「アルカリ電池」が登場すると、ほとんど代替されるようになった。マンガン電池とアルカリ電池が違う点は、電解質(電解液と役割は同じだが、液状でなくなったので電解質と言い換えられた)にアルカリ性の水酸化カリウムが使われることである。起電力が強く、発電反応も速く進む特徴がある。正極が二酸化マンガンであるのは変わらないが、負極の亜鉛粉末から微量だが水銀が溶出する対策として、毒性の少ないビスマス合金を代替利用するようになって今日に至っている。
その次に開発されたのが「酸化銀電池」である。アルカリ電池は放電電圧が時間の経過とともに徐々に下がってしまうことは使用経験がある者の共通認識だろうが、酸化銀電池は一定期間、安定している。正極に銀を使用しているのでコストは高いが安全性に優れ、時計など精密機器や補聴器など小型の製品に適しているが、大型には向かない。
進歩は長期・小型・軽量化
そのため現在は「リチウム電池」に置き換えられつつある。次号で述べる「リチウムイオン電池」と名称が紛らわしいが、違う製品である。充電できるリチウムイオン電池に対して、充電できないことを明示するために「リチウム一次電池」という場合もある。正極は二酸化マンガン等で従来と変わらないが、負極に金属リチウムを使うのが特徴である。従来型と比べ、小型のわりに容量が大きいので(マンガン電池の約10倍)、長期に交換が不要、あるいは難しい用途に適している。ガスや水道のスマートメーター、時計や自動車のリモコンキーなどにはリチウム電池が使われることが多くなった。
ここで一次と二次の違いを述べておく。端的に言えば二次電池が充電できるのに対し、一次電池はできないので使い捨てになるということである。満充電の状態で出荷され、購入されて使用が始まると放電が次第に進み、やがて起電力を失う。消費者が注意しなくてはならないのは、その状態で誤って充電しようとすると、電極の近くにガスが発生して、漏液や破裂が起きてしまうことである。アルカリ電池に使用されている水酸化カリウム溶液は肌に触れるとやけどを起こすので、危険性を認識する必要がある。
本稿は参考資料として、小山昇・脇原将孝『二次電池の本』(日刊工業新聞社、2022年)、神野将志『電池BOOK』(総合科学出版、2019年)、社団法人日本電池工業会ホームページ、等を使用しました。
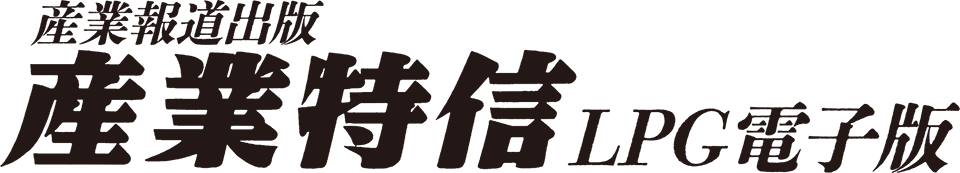

①-120x68.jpg)
