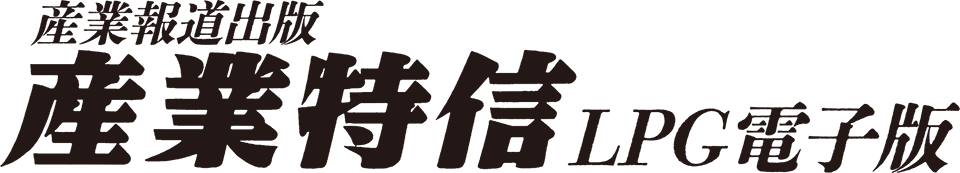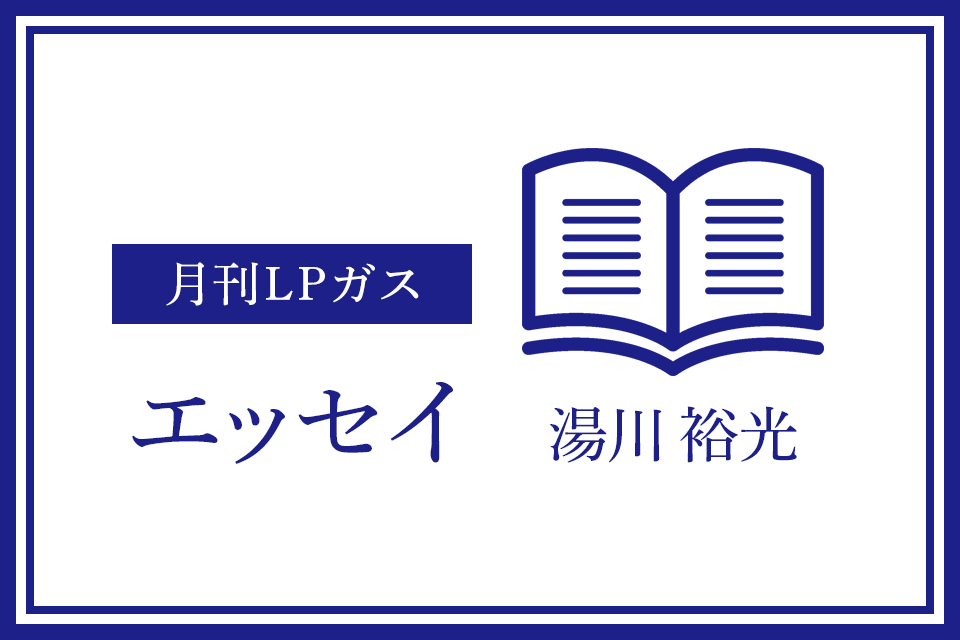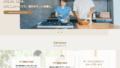月刊LPガス エッセイ★湯川裕光
吉野彰博士がノーベル化学賞を受賞した2019年以降、リチウムイオン電池についての理解と期待が高まった。それを機にパソコンやスマホなど自分たちの生活の身近にある便利なIT機器の、目に見える小型化と軽量化に関わる重要な要素だと知った人が多かったからである。しかし同時に、製造コストが高いことや、原料となる希少資源のリチウムもコバルトも特定の国に偏在している問題(埋蔵も産出もリチウムはチリ、中国、アルゼンチン、オーストラリアの4カ国、コバルトはコンゴ民主共和国とオーストラリア、ロシア、キューバの4カ国)、さらには発火事故の多発など、負の側面も知られるところとなっている。
記事の続きの閲覧は会員(定期購読者)のみに制限されています。全文を読むには ログイン してください。
湯川裕光
作家。1950年、東京に生まれる。東京大学法学部卒業。『安土幻想』『小説古事記成立』など歴史小説を書き、『マンマ・ミーア!』『異国の丘』など、劇団四季のミュージカルの台本も手掛ける。『瑤泉院』は稲森いずみ、北大路欣也主演でテレビ東京の正月10時間ドラマの原作になった。現実政治に携わったこともある。