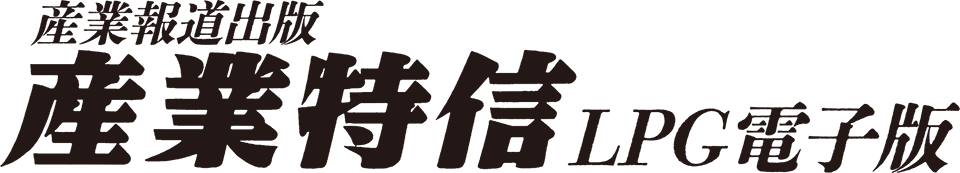令和7年度南関東地方LPガス懇談会が7日、オンラインで開かれ、1都5県(埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡)のLPガス協会会長、消費者団体代表、行政関係者らが参加。保安や料金透明化・取引適正化をテーマに、悪質な訪問販売・点検商法による法定点検への影響や、ブローカーによる切り替え営業の横行など現状と課題を共有した。都道府県による立入検査では、担当者から改正省令の実効性確保を不安視する声も上がったのに対し、資源エネルギー庁が統一基準を作成する意向を示した。
ブローカーに規制を
法定点検について埼玉県協の川本武彦会長は「詐欺の問題でハードルが高くなっている」、山梨県協の望月喜浩会長は「アポを取るのが非常に難しくなっているのが業界の中でも大きな問題になっている」と語った。これに対し埼玉消費者被害をなくす会の柿沼トミ子氏は、法律に基づく点検が4年に1回あるという事実についてLPガス業界が普及啓発を行う必要性を指摘した。全国消費生活相談員協会エネルギー問題研究会の林弘美氏は、「チラシ入れたり、電話でアポを取ったり、訪問したりするのは悪質業者も全部やっている。それと同じことやっていてはダメだ。『あなたのLPガス事業者は私』だということを消費者に分かってもらう頻度でコミュニケーションを」と要請した。
ブローカー問題では、神奈川県消費者の会連絡会の今井澄江氏 が、神奈川県秦野市の切り替え営業チラシを紹介し、「消費者がどんどんだまされてしまう状態にあるので規制をかけていただきたい」と要請した。全国消費生活相談員協会船橋市消費生活センターの山王丸裕子氏も「ブローカーの相談がたくさん入っている」と取り締まりを求めた。
静岡県協の渡邊芳隆会長は、ガス事業者がブローカーを雇っていることを問題視し、「雇わなければこんな問題は起きないので、どこかでやっぱり切り離さないといけない」と断じた。また神奈川県協の髙橋宏昌会長は、警察と連携して対応していく考えを示した。橘川学長は、「過大な営業行為でブローカーが暗躍すると、保安の体制がその時にきちんと引き継がれないという問題も起きる」と警告。液石流通ワーキンググループの今後の活動で「ブローカー規制にメスを入れていくのが一つのポイントになる」と強調した。
立入検査で確認が難しい
都道府県による立入検査では、東京都環境局環境改善部環境保安課の小林伸二郎課長代理が「過大な営業行為があったのかを書類で確認するのは難しい」と報告。神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課の丹羽太一工業保安グループリーダーは、われわれは保安をメインで所管している部門なので、今回の法改正について立入検査でどういうふうに見ていけばいいのかというのは手探りの状況だ。商慣行の部分は踏み込みにくい部分もあり、カネの流れを正直見切れない実態がある」と語った。改善点として「どのように統一的に見ていくのかを示してもらえると動きやすい」と国の対応を求めた。静岡県危機管理部消防保安課の萩原匠主任は、立入検査の実施状況について「特商法などさまざまな法律が横断的になっていて判断が難しい部分もあるので、経済産業省や県協の意見を聞いて、より適正な判断をできるようにしたい」と方針を示した。
資源エネルギー庁資源・燃料部燃料流通政策室の林崎公徳室長補佐は、取り締まり体制の整備について、「関係自治体との協力を進めているが、まだ不十分なところもある。今回の見直しが逆戻りせずに何とか根付いていくような形を考えている。できる限り統一基準を示していきたい」と方針を示した。
橘川学長は、「自治体の方のリソースが足らないことは非常によく分かる」と、都道府県の取り締まりについて〝畑違い〟の保安担当部局が担当している状況に理解を示しつつ、「取引適正化をきちんとやっていない事業者は、だいたい保安をおろそかにしているので、取引適正化問題は保安を確保する上でも重大な問題だ。ぜひ担当者には頑張っていただきたい」とエールを送った。