月刊LPガス 住宅に潜む危険のお悩み問題解決★山岡裕子
はじめに
今年も8月を迎え、お盆が過ぎるとすぐに年末が近づいてきてしまい、あっという間に一年が終わっていってしまうように感じます。今年は7月の初旬に梅雨が明け、早い夏が到来しそこからというもの、暑さに耐え忍びながら皆さん日々を過ごしています。
記事の続きの閲覧は会員(定期購読者)のみに制限されています。全文を読むには ログイン してください。
山岡 裕子
ヤマオカプランニングオフィス代表/リフォームプランナー
エンドユーザーのリフォーム物件を手掛けながら、企業へのリフォーム事業のアドバイザーも行う。建築士、インテリアコーディネーター、整理収納アドバイザー1級
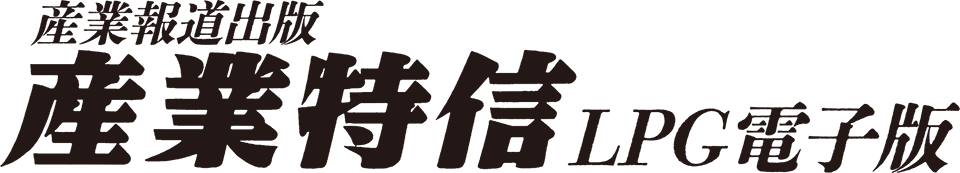
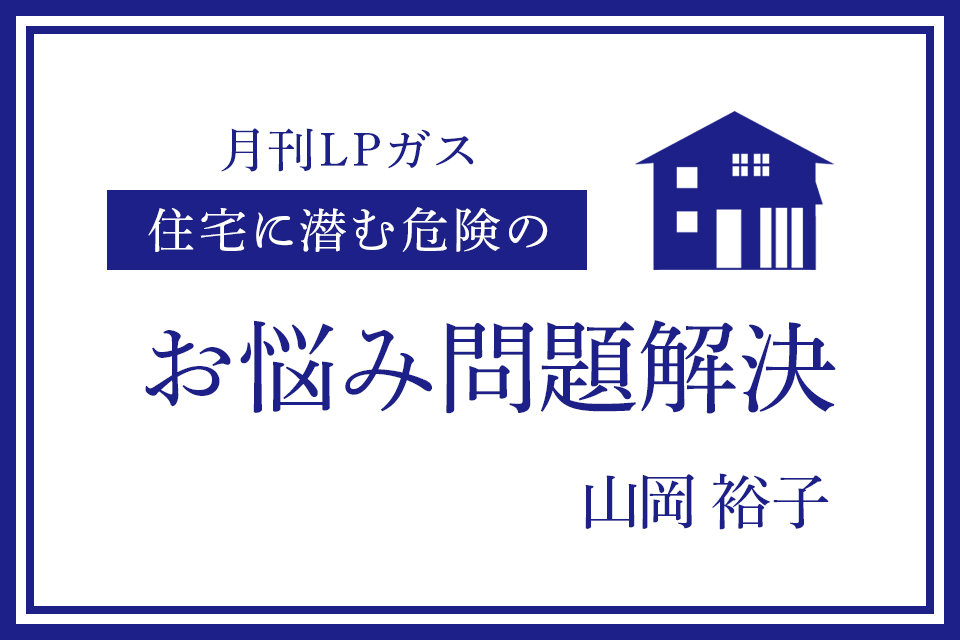

付号_ページ_01-120x68.jpg)