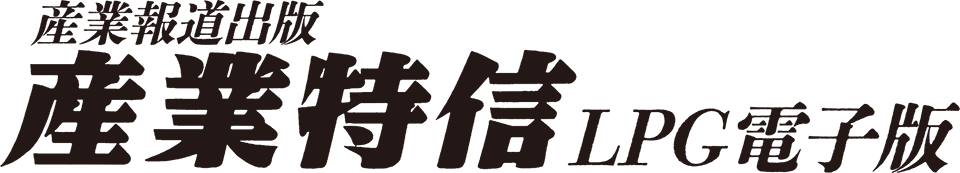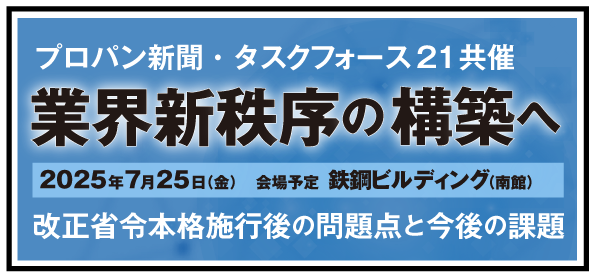タスクフォース21 6月例会で論点整理
ガス体エネルギー事業者の情報交換の場「タスクフォース21」は6月4日、第168回例会で液石法改正省令の本格施行に伴う課題について議論した。7月25日の特別例会(プロパン新聞共催「改正省令セミナー」)に向け、当日のパネラーでもある角田憲司氏、境野春彦氏、中田英穂氏、中川順一氏による論点整理が行われた。
4月から施行された三部制料金制度について、角田氏は「事業者の対応状況は断片的にしか把握できていない」と懸念を示した。関東、近畿、中部地域では本省からのアンケート調査が実施されているが、全国的な実態は不透明だ。「液石WGでは立ち入り検査もあったとしているが、実際にどのような確認や指導がなされているか、全く情報が入ってこない」と指摘した。
現場での混乱を象徴するのが、都道府県レベルでの指導内容の相違だ。境野氏は「県によって対応が極めてばらばら」と問題点を指摘。ある県では「設備料金はゼロにしなさい。他社もやっているのだからゼロにしろ」という誤った指導が行われたという。「これは言語道断で、無償対応がある場合はきちんと外出し表示しなければならない」と強く批判した。
実際の料金設定について、中田幹事は設備料金をゼロ円で表示する事業者がある一方で、基本料金から200円や300円を別建てにする事業者も多いと説明。ただし算定根拠については「明確な根拠はない。周囲の動向を見ながら同程度に設定するという状況だ」と、明確な基準がない実態を報告した。
新規の設備無償対応禁止については、境野氏は「表面的には停止したと言うが、関係を断ち切れない不動産会社があり、継続している部分もある」と説明。中田幹事は「集合賃貸住宅の新築案件のほとんどが受注できず、LPガス業者はほとんど獲得できていない」と厳しい見方を示した。消費者の反応については「1万件規模の事業者で3部料金に関する問い合わせがわずか2件だった」と限定的であることを報告した。
中川事務局長は「現場での解釈や対応にばらつきがあり、事業者間の温度差によるトラブルが発生している」問題を改善するための提言をまとめることも目的に、①三部制料金制の徹底に関する現状と課題②オーナー等への新規設備無償対応禁止の遵守状況③LPガス省令改正後の競争環境の変化――の3点を7月特別例会の主要テーマとすることが確認された。