持家が堅調 分譲は減少続く
住宅は減っても貸家率は上がる!?
国土交通省が公表した2024年度(令和6年度)の「建築着工統計調査報告」によると、同年度の新設住宅着工戸数は全国で81万6018戸となり、前年度比2・0%増と3年ぶりのプラスに転じた。持家と貸家が堅調に推移した一方で、分譲住宅は2年連続で減少した。
持家は22万3079戸(1・6%増)、貸家は35万6893戸(4・8%増)とそれぞれ3年ぶりの増加。分譲住宅は22万9440戸で2・4%減。内訳では、マンションが10万5227戸(5・0%増)と回復基調を示す一方、一戸建ては12万2319戸(8・5%減)と大幅に減少した。
民間の非居住建築物においては、店舗は増加したものの、事務所や工場、倉庫の着工床面積が減少し、全体として3年連続のマイナス。建築工法別では、ツーバイフォー工法の住宅が9万8923戸(7・9%増)と3年ぶりに増加したが、プレハブ工法は9万3833戸(6・7%減)で3年連続の減少となった。
民間の非居住建築物は、店舗は増加したものの、事務所や工場、倉庫の着工床面積が減少し、全体として3年連続のマイナスとなった。
元年度比で7・7%減
全国の新設住宅着工戸数は、令和元年度(2019年度)の88万3687戸と比べて約6万7000戸(7・7%)の減少。利用関係別では、持家が元年度の7万3107戸から約15%減、貸家は約26%減少している。一方、マンション(分譲集合住宅)は元年度の11万1615戸に比べ5・7%の減少にとどまった。
分譲住宅のうち、分譲一戸建ては元年度の25万9732戸から52・9%の大幅減。特に分譲戸建の減少が、全体の減少傾向に大きく影響したとみられる。
全体の着工床面積は6283万㎡で、令和元年度(8846万㎡)と比べ29%近く縮小。住宅着工は2020年度以降、コロナ禍の影響を受けて落ち込んだが、令和6年度はようやく持ち直しの兆しを見せているものの、依然として令和元年水準には戻っていない。
賃貸需要の多様化
一方、住宅の利用係別では、貸家だけが増加しており、令和元年度の33万4509戸に対して、6年度は35万6893戸と約6・7%の伸びを記録している。
この背景には、不動産投資への関心の高さがある。金融庁の「資産形成に関する調査」(2023年)によれば、個人投資家の約4人に1人が「不動産を長期安定資産と見なしている」と回答。また、国土交通省の「土地白書(令和5年版)」でも、相続税対策や節税を目的としたアパート建設の増加が指摘されている。
さらに、住宅取得を避ける若年層や単身世帯の増加も要因の一つ。内閣府「令和5年版少子化社会対策白書」では、30代の持ち家率が20年前よりも大幅に低下しており、雇用の流動化や非正規雇用の増加が「賃貸選好の一因」として挙げられている。加えて、全国で単身世帯が全体の約4割を占めるとの総務省「2020年国勢調査」の分析も、集合型貸家への需要を裏付けている。
また、建築資材の価格高騰や住宅ローン金利の先高観から、分譲住宅や持ち家購入の意欲が鈍化し、開発業者が貸家事業にシフトする動きも見られる。住宅ローン利用者の減少傾向は、日本銀行「金融システムレポート(2024年4月)」でも指摘されている。
投資・相続・世帯構成の変化など、複合的な要因が貸家着工増加を後押ししているが、今後もこの傾向が継続するかは、住宅政策や税制の動向が左右するとの見方がある。一方で、「住宅は減っても貸家率は上がる傾向が続く」と予測する不動産事業者も多い。
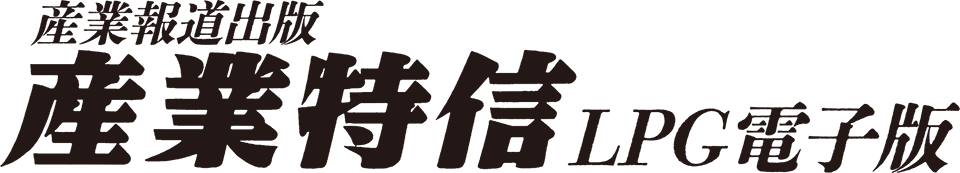

付号_ページ_01-120x68.jpg)
